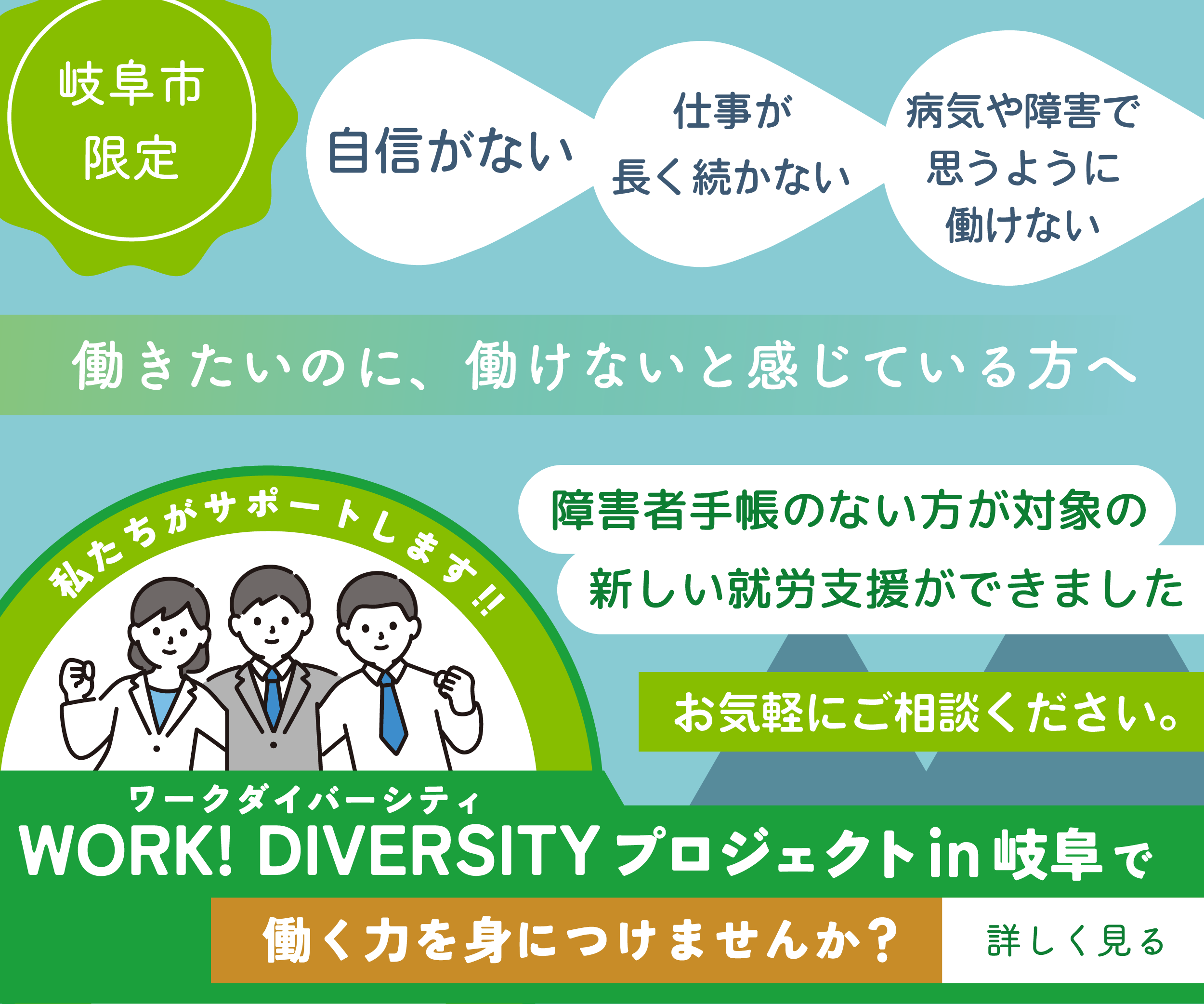障がいがあると、体調や特性により、どうしても働ける場や仕事が限られてしまいがちですよね。
福祉的な受け皿として機能している就労継続支援A型・B型事業所では、最低賃金やそれ以下の工賃しか得られず、生活が困窮する方も少なくありません。
作業所で働く方の中には生活保護を受給する利用者もいますが、そもそも作業所で働きながら生活保護を受給することはできるのでしょうか?
- 生活保護とはどのような制度?
- A型・B型作業所で働きながら生活保護を受けることはできるのか?
- 生活保護の勤労控除
について解説します。
生活保護制度とは
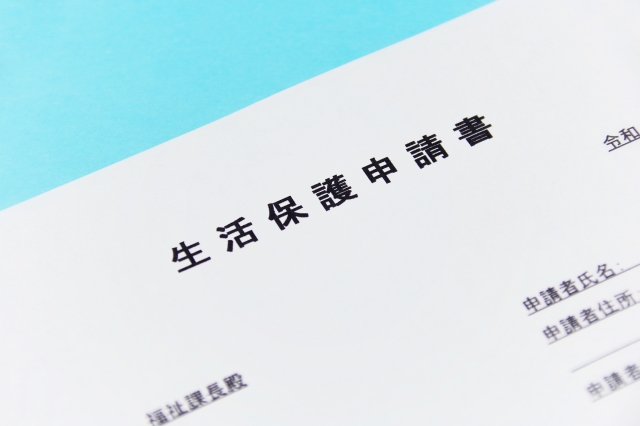
生活保護とは、病気やけがなどが原因で働くことが困難な方、働いても必要な生活費を得られない方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。
生活保護制度|厚生労働省
生活保護費は毎月支給されますが、金額は居住地の等級や世帯人数によって金額が変わります。また、障がいの有無や介護・医療扶助などのさまざまな加算要件がある他、保護開始時に持ち合わせがない場合や冷暖房が無いために健康被害が出た場合など、例外的に一時扶助が認められることもあります。
受給資格を得る前に、年金など、他の制度での救済が可能ではないか、預貯金や生活に利用していない不動産などの資産を売却することで生活費を捻出できないか、などを検討されます。
受給を希望する場合、福祉事務所を通して世帯単位で申請し、(生活保護法第28条に基づいて)ケースワーカーや福祉事務所の職員によって生活の管理をされます。
例えば、生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告する必要があります。また、1年に数回、福祉事務所のケースワーカーが訪問調査を行い、制度上のルールを逸脱していないかチェックされます。さらに、就労の可能性がある方の場合、就労に向けた助言や指導を行う場合もあります。
生活保護の申請は国民の権利として認められています。生活保護を必要とする可能性は誰にでもあるものなので、当てはまるかわからない場合でも躊躇せず、お住まいの自治体にある福祉事務所の生活保護担当へ相談しましょう。福祉事務所が設置されていない町村の場合、町村役場でも申請手続きを行うことができます。
生活保護の種類
生活保護費の内訳は8項目に分類されます。
| 費用内容 | 支給内容 | |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) |
基準額は 1.食費等の個人的費用 2.光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出 特定の世帯に加算あり (母子加算等) |
| 住宅扶助 | アパート等の家賃 | 定められた範囲内で実費を支給 |
| 教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費 | 定められた基準額を支給 |
| 医療扶助 | 医療サービスの費用 | 費用は直接医療機関へ支払い (自己負担なし) |
| 介護扶助 | 介護サービスの費用 | 費用は直接介護事業者へ支払い (自己負担なし) |
| 出産扶助 | 出産費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
| 葬祭扶助 | 葬祭費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
生活扶助は受給者の生活費であり、以下の4項目で構成されています。
- 生活扶助基準額
- 加算(母子家庭、妊婦、障がい者など)※
- 入院患者日用品費(寝間着、タオルなど)
- 一時扶助(被服費、移送費など)
※母子加算と障害者加算は原則併用できません。
生活保護が支給される基準
世帯収入が居住する地域の物価などから算出された最低生活費を下回る場合に、受給資格が生まれます。住居地と世帯人数によって資格を得られるかが変わります。
例えば、東京都の区内で30代、1人暮らしの場合、月13万円程度が最低生活費となるため、毎月の収入が13万円以下だと受給資格を得られます。
原則として、働くことが可能であれば就労により生活費を捻出し、年金や手当などを受けられる場合、他の制度の活用や、預貯金や生活に利用していない土地・家屋などの資産を活用することも求められます。それでも足りない場合、不足分を生活保護費として受給することになります。
また、親族等から援助を受けられる場合、受給資格は得られません。
親族の扶養義務
生活保護を申請すると、両親や親戚に当事者を扶養できるか「扶養照会」の連絡が入ります。
あらゆるものを活用してそれでも最低生活費を捻出できない場合に支援を行う制度のため、一部の事例※を除いて扶養照会を避けることはできません。扶養されることができる場合、生活保護の受給も見送りとなります。
※一部の事例扶養照会を避けることができる例として、「扶養義務履行が期待できない者」かどうかがあります。
- 扶養義務のある方が、生活保護を受けている、社会福祉施設入所者、長期入院患者、専業主婦・主夫などのように主たる生計維持者ではない非稼働者、未成年者、70歳以上の高齢者などの場合
- 生活保護を求める方の生活歴などから特別な事情があり、明らかに扶養ができない場合
(例:扶養義務者に借金を重ねている、扶養義務者と相続をめぐり対立しているなどの事情、縁を切られているなど、著しい関係不良の場合など。) - 扶養義務者に扶養義務を求めることで明らかに保護を申請した方の自立を阻害することになると認められる者
(具体的にはDV、虐待のある場合。配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律第二十三条などに基づき、生活保持義務関係にある扶養義務者でも、扶養の可能性が期待できないものとして取り扱うことになっている。)
生活保護を受ける手続きの流れ
この項目では、生活保護を受けるための手続きの流れを解説します。
- STEP1事前相談生活保護制度を利用したい場合、居住地の地域を管轄としている福祉事務所に行き、生活保護担当へ行きましょう。生活保護制度の説明と共に、生活福祉資金、各種社会保障などの活用を検討してもらえます。
- STEP2保護申請生活保護を申請した方について、保護を行うか決めるために以下のような調査が実施されます。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問など)
- 預貯金、保険、不動産などの資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性調査
- STEP3保護費の支給
- 事前に定められた基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入など)を引いた額が保護費として毎月支給されます。
- 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告する必要があります。
- 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回訪問調査を行われます。
- 就労の可能性がある方の場合、就労に向けた助言や指導も行われます。
次の章から、作業所に通いながら生活保護を受けることができるのか、を解説していきます。A型・B型作業所(就労継続支援事業所)がよくわからないという方は、以下の記事をご覧ください。
⇒就労継続支援とは?サービス内容やA型・B型の違いを徹底解説
[
A型事業所に通う場合、打ち切られる可能性が高い
A型作業所に通いながら生活保護を受けることは難しいです。
A型作業所は雇用契約を結び、最低賃金以上の給与がもらえるので、安定した就労とみなされる可能性があります。
A型作業所での就労収入が生活保護の受給額より少なくても、障害年金を受給して、就労収入と障害年金の合計金額が最低生活費を上回る場合、A型作業所に通所しながら新たに生活保護を受給することは不可能です。
既に生活保護を受給している方の場合、福祉事務所の判断によってはA型作業所に就職することで保護を打ち切られる可能性もあります。
原則、就労により生計を立てられない方のための救済制度が生活保護であるため、1人世帯で雇用契約を結び、安定就労している方は保護の対象外となります。
生活保護費は収入に応じて減額になる
生活保護費は世帯単位で算定され、人数や年齢、障がいなどの身体状態、および収入の状況に応じて月ごとに計算され、決まります。
ここでの「収入」とは、働いて得た就労収入だけでなく、年金や仕送り、賭け事での突発的な収入など、世帯員全員が得たものが全て収入となります。どのような収入でも、生活保護を受給する以上、申告する義務があります。
生活保護費から、申告した収入金額分が差し引かれ、減額処理がなされます。つまり、最低生活費と収入の差額分が支給金額となります。
生活保護の勤労控除
せっかく頑張って働いても生活保護費が減額されてしまうならやる気が無くなってしまいますよね。
しかし、就労で得た収入はその金額に基づいて、控除がされます。就労に伴う必要経費を補填する目的であり、世帯の収入認定額が控除される分少なくなります。つまり、使えるお金が少し増える、ということですね。
勤労控除には以下の種類があります。
| 基礎控除 | 仕事をする上で発生する、さまざまな「必要経費」を見込んで、収入認定額から一定金額が除外される。 収入に応じて段階が細かく決められている。 |
|---|---|
| 未成年者控除 | 未成年が就労している場合、未成年の勤労収入から控除される。 単身の場合、児童福祉法が先に適用されるため、生活保護の認定がされない可能性がある。 |
| 新規就労控除 | 中学・高校卒業後、就職時に臨時で必要な分は就職支度費で対応するが、就職後、職場に適応するまでの身の回り品の確保などのため、6か月間に限り控除される。 また、入院などやむを得ない事情のために長期間就労できなかった方が就職する際にも適用される。 |
| 必要経費 | 働くために必要な、通勤時の交通費や年金、社会保険料、各種税金、労働組合費など、さまざまな経費が対象。 雇用されている場合は、収入から基礎控除を算定し、必要経費分を収入から除外することになる。 |
B型作業所で工賃が一定金額を超えると生活保護費の減額対象に
B型作業所では雇用契約を結ばないため、給与ではなく工賃が出ます。
働く時間の融通が利く代わりに、最低賃金は適用されず、工賃は低いことが多いです。
⇒就労継続支援B型はどんな人が利用対象?B型事業所の利用方法を詳しく解説
B型作業所に通いながら生活保護を受けることは可能ですが、工賃が月額15,000円を超える場合、収入と認定されます。収入として認定された分は生活保護費から差し引かれます。
この15,000円は勤労控除の一種です。B型作業所での工賃が月額15,000円以下であれば全額控除となり、使えるお金は増えます。
支給される交通費は収入に含まれない
交通費は就労に必要な経費とみなされるため、実費で控除となります。
交通費として控除されるのは実費分のため、給与明細に表記される通勤手当がそのまま控除対象になるわけではないため、注意が必要です。
生活保護だと非課税になる?
生活保護を受給すると、以下の税金・公的支払いが減額・免除されます。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 固定資産税
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
- 自動車税
- 保育料
生活保護を受けると、多くの公的支払いが減免されます。ただ、年金は支払った分しか受け取ることができないため、年金を満額で受給したい場合は追納を行う必要があります。
その他、以下の公共料金も支払い免除や割引がされます。
- 介護・医療費
- 上下水道料金(一部の地域のみ)
- NHK放送受信料
- 葬祭費用
- JR定期券(通勤用)
障害年金と生活保護の併用は可能だが、減額される

生活保護と障害年金の制度を併用することはできます。
生活保護の制度上、年金も「収入」として取り扱われるため、障害年金を受給している間、生活保護費を満額受給することはできません。生活保護費は最低生活費から年金の額を差し引いた金額が支給されます。
ただ、障がいがある方の場合、障害者加算がされる可能性があります。
障害者加算の額は、居住地の等級や障がいの重さによって異なります。
| 1. に該当する方 | 2. に該当する方 | ||
|---|---|---|---|
| 在宅者 | 1級地 | 26,810円 | 17,870円 |
| 2級地 | 24,940円 | 16,620円 | |
| 3級地 | 23,060円 | 15,380円 | |
| 入院・入所している方 | 22,310円 | 14,870円 | |
参照:【PDF】障害者加算|2023(令和5)年4月1日施行 生活保護実施要領等
※2023年時点の情報のため、金額等は変更になる可能性があります。
生活保護の考え方として、最初に他の制度による支援を検討・活用し、不足する分を生活保護で補う、というのが基本となっています。
障害年金単体には所有財産の制約や収支報告義務がないため、生活保護と比較すると自由度が高いと言えます。
障害年金のみを受給するのであれば、生活保護のデメリットを負うこともなく、A型作業所での就労で最低生活費分を捻出できます。
回復の見込みがある場合、将来設計をしながら受給を検討するのが望ましいでしょう。
まとめ|A型・B型作業所に通うと生活保護は打ち切られるのか
- 生活保護は、病気やけがなどが原因で働くことが困難な方、働いても必要な生活費を得られない方に対して、困窮度合いに応じて健康で文化的な最低限度の生活を送れるように保障を行う制度。不動産や貯蓄型保険、ある程度の預貯金などの資産がある場合、処分する必要がある。
- A型作業所に通う場合、障害年金と合わせた収入認定額が最低生活費を上回る可能性があるため、生活保護を受けられないことがある。B型作業所に通う場合は、生活保護を受けられるが、障害年金や工賃の関係で生活保護費が減額になる可能性はある。
- A型・B型作業所で働く場合でも勤労控除が適用されるため、収入認定額が低くなる可能性がある。
以上、生活保護の知識と、生活保護を受けながら作業所で就労する場合についての解説でした。
障がいがある方が働ける場所は法定雇用率が改正されたことで増えつつありますが、まだまだ少ない状態です。また、作業所で就労するとしても作業所の収入と障害年金を合わせても生活するのが難しい場合もあります。
生活保護に限らず、必要に応じて使える制度を利用していきましょう。